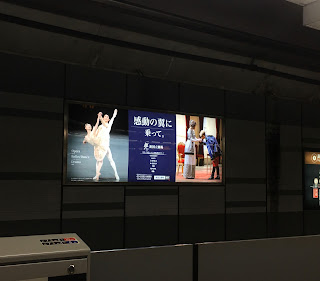日本バレエ協会公演コンテンポラリーとクラシックで紡ぐ眠れる森の美女を2日間観て参りました。例年はこの時期文化会館での協会公演は全幕物上演ですが
今年は現況でも実現できる企画として、前半は遠藤康行さん振付コンテンポラリーLittle Briar Rose(いばら姫)、
後半は篠原聖一さんによる古典(オーロラ姫の結婚)を上演です。
http://www.j-b-a.or.jp/stages/2021都民芸術フェスティバル参加公演/
ダンススクエアに多数の舞台写真付きの記事が掲載されています。当たり前ですが当ブログより遥かに分かりやすい説明ですので、是非ご覧ください。
https://www.dance-square.jp/jbes1.html
プロの優れた執筆を読んだ後であっても素人の欠陥多数な文章を読む気力のある方は以下ご覚悟と忍耐の上、どうぞお読みください。
※キャスト等バレエ協会ホームページより抜粋
【第一部】 Little Briar Rose(いばら姫)
音楽:ピョートル・チャイコフスキー 他
振付・構成・演出:遠藤 康行
美術:長谷川 匠
音楽監修:平本 正宏
衣裳:朝長 靖子
バレエ・ミストレス:梶田 留以
アシスタント:原田 舞子
Cast
オーロラ:木村 優里
王子:渡邊 峻郁
カラボス<マジシャン>:高岸 直樹
梶田 留以 金田 あゆ子 木ノ内乃々
柴山 紗帆 原田 舞子 石山沙央理
石原 一樹 磯見 源 上田 尚弘 岡本 壮太 南條 健吾
小幡 真玲 南 帆乃佳 田代 幸恵
井後麻友美 海老原詩織 橋本まゆり
コンテンポラリー版いばら姫は、待っているだけでない能動的な姫と誠実そうな王子が出会い、
ローズアダージオとほぼヴァイオリンソロの間奏曲を使った濃密で長いパ・ド・ドゥを軸に出会い、試練を経て結ばれるまでを展開。
要所要所にカラボスや6人妖精も絡み、凝縮版として面白味のある作品でした。
オーロラ姫の木村さんはワルツを踊る人々の中へ序盤から好奇心旺盛な様子で入って行き、今回の版で遠藤さんが理想とする能動的な姫像をくっきりと造形。
大概の人ならばコスプレ大会での大コケ姿露呈状態となるであろう奇抜にもほどがある紫やピンクがかった三つ編みの鬘や
かぼちゃ型を模したパンツの衣装でも着こなせていたのは木村さんの生来の可愛らしく麗しい、抜群に長い四肢からなる容姿だからこそでしょう。
一瞬度肝を抜かれましたがフィギュアのようにも見え、それだけさまになっていたわけです。
コンテンポラリーはまだそう経験豊富では決してないはずですが、錚々たるダンサーに囲まれても埋没せぬ姿にも驚きを覚え
しなやかに動く身体が熱を帯びて観客の目を吸い寄せる魅力を示し、このオーロラと同様恐れずに飛び込んでいくチャレンジャー精神に天晴れでした。
渡邊さんは銀髪銀色スーツでこれまた大仰天でしたが、お詳しい方々曰く宝塚歌劇団で見られるようなデザインでも着こなす容姿は稀少であるとのこと。
(実は管理人、宝塚の舞台鑑賞未経験ですぐさま思い浮かばず。一昔前の歌謡歌手だの頓珍漢な例ばかり挙げており大変失礼いたしました)
衣装話はこの辺りにして、出演者の殆どが舞台上に集まり床に伏せた状態で始まる花のワルツ序盤から軽やかさと強さが共存し
手脚の長さを持て余さず無駄なく駆使していく身体の使い方と言い、抜きん出たレベルにいらっしゃると見て取れ
淀みない流れの中でいつの間にか跳躍し宙を舞っていた瞬間も多数。
トゥールーズのキャピトル・バレエ団在籍時代におけるコンテンポラリーも
大変経験豊かな方でありながら新国立劇場での公演では滅多にご披露の機会がなく、約40分踊り通しのお姿を拝見でき感激もひとしおです。
更にはただ身体能力を駆使するにとどまらず、今回の公演テーマの文字通りコンテンポラリーで物語を紡ぐ力にも驚倒。
勿論、バレエ団公演で好評を博している組み慣れた木村さんとの相性の良さもさることながら
オーロラ姫のほうが見た目も、古典とは違った役の解釈で重みが置かれていると思いがちな作品の中でも
姫との出会いにおける立ったまま向かい合っているだけでみるみると感情が押し迫るように高揚する様子が伝わり
カラボス達から逃れようと走っていく姿はなかなか独特のフォームでしたが笑、走行姿はともかく音楽に対して身体の反応がいたく敏感で
一瞬一瞬において残る鮮烈な余韻にも身震いするほどに感激。
混沌と入り乱れた設定の舞台上でも物語を牽引し突き動かす人物として確立し、古典のようにリラの精による舟の送迎もお膳立てもなく身体を張って立ち向かい
打ち負かされそうになっても尚めげすに突き進んでいく心理や状況描写も的確で
最初は目を疑ってしまった銀色スーツどころではもはやなくなったくらいです。
さて、協会公演でもやります髪型観察。今回は銀髪な異例事態となりましたが二重丸。
自然な分け目でペッタリ具合も無し、難しい色合いでもきらっとした銀がまた良かったのでしょう。
王子であり若く溌剌とした青年にも見え、『ロメオとジュリエット』パリスを除いては黒髪の印象しかない
しかもお醤油顔ながら銀でも映えるのは容貌がいかに端正であるか再証明しているといって過言ではないでしょう。
作品の核となっていた見せ場がローズ・アダージオとヴァイオリンほぼソロの間奏曲を用いた2つのパ・ド・ドゥ。
前者は出会って間もないオーロラと王子の距離感が一気に縮んでいくさまを壮大に描き、オーケストラの楽器総動員な仰々しいほどにスケールのある
本来は姫の友人や両親、求婚者達、貴族達、と立ち役含む大勢の出演者に囲まれた豪華な誕生会に似つかわしい音楽を
舞台上でたった2人であっても冗長さを感じさせずに作り上げた力量にまず賛辞を送らずにいられず。
しかも身体を濃密に絡ませたり、危険そうなリフトや構造が見えぬ複雑なサポートも多岐に渡る振付ながら木村さんが無防備に飛び込んでいったり、
どの場であっても盤石に受け止め場合によっては背中に乗せたままそのまま走る箇所も興奮が噴水のように溢れる王子の心の内側を覗かせるように
サポート姿でさえも渡邊さんは美しく魅せ、力んでのサポートや頑張って走っている感も皆無でお2人の実力と互いの信頼感の結晶と想像。
曲の起承転結といよいよ結ばれる姫と王子のときめき感が調和し、物語の流れの鮮やかな表現に息を呑むしかありませんでした。
間奏曲はライト版やウエストモーランド版、イーグリング版など英国系列の演出では目覚めのパ・ド・ドゥとして使用されていますが
混沌とした世界が過ぎ去った後の安堵と愛情を確認しあう空気感を柔らかく描き、古典におけるお2人の目覚めも過去に鑑賞しておりますが、
空間を大きくより自由度が高まった今回のパ・ド・ドゥも宜しく、最後は王子が姫を抱いたまま幕。そして第2部『オーロラ姫の結婚』へバトンを繋いだのでした。
ふと思ったが、渡邊さんならば新国立劇場エメラルド・プロジェクトで上演され高い評価を得ながらも一度も再演されていない
ドミニク・ウォルシュ振付『オルフェオとエヴリディーチェ』ができると思っており
第2幕には互いに目を合わせてはならぬ極限状態で踊る20分以上に及ぶ壮絶なパ・ド・ドゥが用意され
パ・ド・ドゥ名手の渡邊さんならば物語の世界やオルフェオの心理を深く描きながら出来ると確信しており、いつの日か観たい役柄です。
カラボスの高岸さんは元々の上背が威圧感と共に文化会館入口からも見えるスカイツリーの如き巨大な存在感。
黒く豪奢な衣装に負けぬ堂々たる立ち姿で、身体もまだまだ俊敏に動き、姫や王子に容赦なく試練を与える、誰も勝てそうにない強敵カラボスでした。
尚高岸さんの責任ではありませんが、マジシャンの呼び名の由来が今一つ分からずであったのが心残り。
妖精達の配置もユニークで、古典ではオーロラの赤子時代にしか勢揃いしない6人の妖精達がパ・ド・シスの音楽に乗せて、
オーロラに寄り添い、オーロラも興味津々に幸せそうに恵みを受け取るやり取りにも注目。
またただ魔法を優しくかけるだけでなく、カラボスの奇襲から逃れようと奮闘する姫と王子を囲い守る勇ましい戦士な役割も。(セーラームーンか笑)
リーダー格が紫であるのは古典からの踏襲で分かりやすく、それぞれ赤や緑、青など色とりどりのワンピース風衣装でお洒落な装いと映りました。
髪型も体型もそれぞれ自由で専門舞踊も皆異なっていても自然と和を保つ、不思議な魅力も堪能です。
それから最も危惧していた遠藤さんの振付名物、謎の長き静謐時間が今回は抑え目であったのは幸い。
2018年に新国立劇場で開催され遠藤さんが主に振付指導にあたっていらしたジャポン・ダンス・プロジェクト『夏ノ夜ノ夢』2幕の約半分が
無音の中で出演者が「ブハッ」と息つぎする展開で、コンテンポラリー不慣れな私がいかんのだが、せっかく心から虜になっているダンサー出演舞台
しかも間近で下着1枚衣装でありながら、本来ならば崇めて拝んで鼻血が心配な状態になろうはずがとても至らず苦行に近い鑑賞となってしまったのでした。
しかし今回も似た路線の場面はあったもののそう長くは無く、また上から降りてくる装置を各々取り外し
フラフープのように持っては床に倒れ顔にフェイスカバーのような布を被せるといった
意図は深くは理解できすとも、実体が未だ解明されずにいるウイルスによる支配や抑圧に苦しむ今の時代に語りかけているとも捉えられる展開で、
遠藤さんによる現代社会の鋭い描写が私の目や心にもすっと入り、集中して鑑賞。苦行と呼び失礼極まりなかった笑、3年前とは大違いでした。
※ご参考までに、当時の舞台の様子が気になる方は
こちらをどうぞ。
オーロラ姫と王子の出会いに一捻り加え、眠りの御伽噺な世界観はそのままにチャイコフスキーと平本さんの音楽を切り貼り感なく合わせ
現代の問題を無理矢理ではなくさりげなく問いかけるような要素も組み込んで展開する
斬新でありつつも普段バレエを中心に観ている私のような客層も変に肩肘を張らず、すんなりと入りやすいコンテンポラリー作品でした。
ところで、このところ渡邊さんは今回の王子や、2月公演のデジレ王子にしても、戦闘能力が頗る抜群そうな王子とは言い難いのだが
過去には今回のプログラムの出演者紹介ページの舞台写真にも載っているベジャール版『火の鳥』や(新国立での写真を希望するお声もあるでしょうが私は嬉しい)
『海賊』スルタン、『美女と野獣』野獣など、近寄り難く豪胆な人物やいたく雄々しい役柄も数々踊っていらっしゃり
中でもスルタンは泣く子も黙るおっかなく冷酷な、素手でねじ伏せられそうな暴君で
これまでに観た歴代の悪役敵役ではボリショイのゲディミナス・タランダのアブデラーマンに並ぶインパクトで初めて映像を目にした日は大事件勃発な1日、
当時20代前半であったご年齢も到底信じ難い衝撃であったのは事実で貫禄や凄みをいかにして体現なさっていたのか疑問が絶えず沸き続いたのは事実です。
弱小ヒーロー(失礼)から正反対の一癖も二癖もある悪人まで、
役柄の引き出しが多く振り幅が広い魅力に再度興奮を覚えた次第でございます。
【第二部】 オーロラ姫の結婚
音楽:ピョートル・チャイコフスキー
振付・構成・演出:篠原 聖一
振付補佐:下村由理恵
バレエ・ミストレス:佐藤真左美
Cast
<オーロラ姫> 酒井 はな(6日) 寺田亜沙子(7日)
<デジレ王子> 橋本 直樹(6日) 浅田 良和(7日)
<リラの精> 平尾 麻実(6日) 大木満里奈(7日)
<フロリナ王女> 清水あゆみ(6日) 勅使河原綾乃(7日)
<青い鳥> 荒井 英之(6日) 高橋 真之(7日)
<白い猫> 岩根日向子(6日) 寺澤 梨花(7日)
<長靴を履いた猫> 田村 幸弘(6日) 江本 拓(7日)
<赤頭巾> 橋元 結花(6日) 清水 美帆(7日)
<狼> 荒井 成也(6日) 小山 憲(7日)
<王妃> テーラー 麻衣
<フロレスタン王> 小林 貫太
<式典長> 奥田 慎也
<宝石の精>
大山 裕子 玉井 るい 吉田 まい ヤロスラフ・サレンコ(6日)
渡久地真理子 古尾谷莉奈 渡辺 幸 加藤 大和(7日)
<マズルカ>
青島 未侑 金海 亜由 金海 怜香 栗田 陽南
小林 由枝 染谷 智香 須貝 紗弓 中村 彩子
深山 圭子 細井 佑季 宮本 望 山内 綾香
石原 稔己 オリバー・ホークス 川﨑 真弘
草薙 勇樹 小林 治晃 高橋 開 竹本悠一郎
秦野 智成 安田 幹 安中 勝勇(以上両日)
加藤 大和 小山 憲(6日)
荒井 成也 田村 幸弘(7日)
<貴族>
大塚 彩音 小野田奈緒 佐藤 愛美
田代 夏花 寺坂 史織 野澤 夏奈
八木真梨子 林 彥均
古典版は第3幕「オーロラ姫の結婚」。3年前に札幌での旧北海道厚生年金会館(ニトリホール)閉館公演にて篠原聖一さんが国王役で出演された
結婚式場面を鑑賞しておりますが、篠原さんが関わっていらっしゃるためか似た路線の演出で、王道なる絢爛な式が繰り広げられました。
オーロラ姫の酒井さんは幕開けの登場時に腕を掲げたときから花を開かせるように艶やかな風を起こし、気品香り立つ姫君そのもの。
特に国王と王妃や貴族達全員に目配せをして祝宴を更なる纏まりへと繋げ、舞台の格を増幅です。
ただ、私が酒井さんのオーロラといえば舞台でも写真でもマリインスキー系の版で見慣れているせいか
今回のロイヤルスタイルはやや違和感があり、いつもの大輪の花の如き晴れやかなステップは抑えめであったかもしれず
ヴァリエーション冒頭でもパッセではなくダイナミックなアチチュードのポーズで引き込む姿が観たいと思わず欲が募ってしまったのは正直なところ。
そうは言っても先述の通り、宮廷の人々との視線の交わしや指先から幸せの花々が零れ落ちるような幸福感は酒井さんのオーロラの真骨頂。
至福のひとときであったのは間違いありません。光沢のある白い布地にピンクの薔薇が添えられた衣装もたいそうお似合いでした。
橋本さんのデジレ王子は昨年のバレエ協会全幕『海賊』に比較すると酒井さんとの呼吸の合い方に少々ずれを感じたのは否めずでしたが
からっと明るい王子を造形。貴公子系よりもキャラクターの濃い役の方が本領を発揮なさるタイプであるのかもしれません。
寺田さんのオーロラ姫は初見。すらりとしたスタイルに新国立きっての華やかな美貌の持ち主で、姫の中の姫も観てみたかったため期待を持ち過ぎてしまったか
内側からの煌めくオーラよりも不安や緊張な胸の内が露わになってしまっていた印象で、ハラハラと手に汗握る箇所がいくつもあり。
しかし天性の美しさから醸し長い腕が柔らかに描く優雅さや、威風堂々とはまた違うほのかな恥じらいも覗く愛らしさにも魅せられ、貴重な舞台を堪能です。
浅田さんは当初心配していた寺田さんとの身長差はそう感じさせず、パ・ド・ドゥにおいてサポートや立ち位置微調整が上手い対処の効果なのでしょう。
寺田さんの手が長い条件もあって、手先が床に付きそうな状態に一旦なってしまってから浮き上げて止めていた
誠にスリル満点なフィッシュダイブ以外は手堅く纏め上げていらっしゃいました。
リラの平尾さんは役の経験も豊富そうで、出から宮廷を司る妖精らしい統率力を明示。
マイムの間も絶妙で、挿入されたプロローグのヴァリエーションの滑らかに歌うような踊りに魅了され、対する大木さんはにこやかな笑みと長くすらりと伸びる手脚が描く軌跡の美で祝福感を後押し。
お2人とも紫と銀で覆われた豪華な頭飾りや細かい装飾で彩られた衣装もよく合って好印象です。
両日目を見張ったのは白い猫と長靴を履いた猫で、岩根さんと田村さんは登場から達者に繰り返すパ・デ・シャも見事なほんわか仲良しな猫ペア。
寺澤さんと江本さんは隙あればいたずらの応酬が止まらぬ仕掛け満載な楽しいペアでふと静まった瞬間も何をするか面白く観察し
両ペア共通していたのは、宮殿のソファやクッションにて寝転んだりじゃれ合っていそうな品を備えていたこと。
貴婦人や紳士を模した衣装を着るに相応しい猫さん達で、岩根さん寺澤さんは白鬘も違和感皆無な容貌でした。
宝石は玉井さんが頭一つ抜けた洗練された存在感で、力みのない
跳躍やダイヤモンドのカラットを思わせる立体感ある身体の見せ方も秀逸。
協会公演での毎度楽しみな方のお1人、渡久地(とぐち)さんの鮮やかできりりとした踊りも惚れ惚れいたしました。
宝石女性の衣装も宜しく、クラシックチュチュにきらりと光る素材が散りばめられた明快且つ派手過ぎずされど華やぐデザイン。
目は慣れてはきたが、某国立も参考にしていただきたいと願います。
(宝石より先に青い鳥が要早急案件ではあるが)
話が青い鳥の如くあちこちに飛びますが、冒頭で述べたように3年前に旧北海道厚生年金会館(ニトリホール)閉館公演にて篠原聖一さんが国王役で出演された
結婚式場面を鑑賞。概ね似た路線ながら今回篠原さんの改訂によって違う点もありました。
特徴として共通していたのは、国王と王妃や貴族達が童話のキャラクター達を出迎える前に披露するサラバンド。
王朝の栄華を悠然と漂わす効果大で宮廷世界への入り込みに一層繋がっていき、札幌以外でも是非取り入れた演出を観たいと願っていただけに嬉しい共通点でした。
対して異なっていたのはオーロラ姫とデジレ王子登場のタイミングで、札幌では最後の最後グラン・パ・ド・ドゥの段階になって
ようやくの登場でしたが(首を長く長くして待っていた当時を回想)
今回は幕開けに勢揃いしたところで登場。セルゲイエフ版などに見られる、新郎新婦が早々に登場して
赤頭巾ちゃんや青い鳥達始め客人達をお迎えする、私が好きな演出に少し近い形でこれまた喜びでございました。
それから札幌では宝石は女性のみで、シンデレラと王子の踊りが有り。(哀愁がじわりと滴るような曲調がいたく好みですが近年は省略が多く、少々残念。
近年の傾向である上演短時間化事業仕分け真っ先の対象となるのでしょう)
他にも細かな箇所で諸々あるとは思いますがそうでした、今回はアポテオーズにてオーロラ姫とデジレ王子がマント装着。
札幌でも装着ありで観たかったとの欲は尽きませんが終わってしまったものは仕方ない笑。
※札幌での公演の様子が気になる方は、ご参考までに
こちらをどうぞ。
恒例旅日記付きでございますが、クラーク像のある羊ヶ丘展望台には僅か10分滞在、
徒歩ではなく基本小走りでないと間に合わぬ欲張りスケジュールでございました。このとき以降北海道は基本日帰りは無し、と心に決めたものです。
今回の話に戻します。昨年2020年は眠り初演から130年を迎えたためか、昨年から今年にかけて、国内団体による眠り上演が相次いでいる気もいたします。
毎度クラシックの全幕上演が恒例である2月や3月のバレエ協会公演と趣向を変え、例年にはない構成でしたがむしろ喜ばしい人選もあり。
現況だからこそ成し得る公演企画が結果として良い方向へ作用した公演で
しかもコンテンポラリーでは出会いと試練を、古典では結婚式を描き出し第1部からの流れを汲む物語進行形式は斬新で面白味も十二分。
発案に拍手を送りたい思いです。
来年3月の協会公演はユーリー・ブルラーカ版『パキータ』全幕を予定との告知あり。内容が無いに等しい1幕をいかにして描いていくか
15年前のパリ・オペラ座来日公演でラコット版全幕を鑑賞していながらいざこざがあった点やペンダントが鍵となっていた程度にしか
前半の内容は覚えておらず、今から心待ちにしております。

『いばら姫』カーテンコールには撮影時間が設けられ、両日発表会でいえばカメラマンさんが腰掛けるであろう辺りにに着席していながら
我が撮影技術の劣り具合が益々進行しているのか良作なかなか撮れずで悪しからず。舞台の様子の参考までに数枚紹介いたします。


遠藤さん、ご登場。


2日目はズーム中心。


2日間とも、客席開場前にはいばら姫の美術を担当された長谷川匠さんによるギャラリートークもあり。説明を踏まえて鑑賞するとより面白味が高まり
模型製作時は客席も作って観客からの見え方も計算している点や、出演者側からも見ても舞台の世界に浸っていられるよう
裏側まで立体感のある作りにしているなど(もし聞き間違いがあったらすみません)心掛けていらっしゃることを説明してくださいました。
プロフィールによれば1985年生まれとのことで、舞台芸術の美術担当をなさっている方の中では大変お若い年代であるかと思います。

2018年新国立劇場で開催されたジャポン・ダンス・プロジェクト『夏ノ夜ノ夢』パネル。パネル下部の写真、
オレンジ色の衣装を着ていらっしゃるのがライサンダーの渡邊さんです。

『夏の夜ノ夢』模型。きらきらと光る鏡板の吊るしは今もよく覚えております。当時は終演後、舞台装置のみ撮影時間が設けられました。
今回の展示も撮影自由で、長谷川さんが手掛けた昨年末に大和シティーバレエで上演された『美女と野獣』模型も展示されていました。

『いばら姫』模型。長谷川さんは大変気さくでチャーミングな方で、自らペンを手にサインしますと呼びかけていらっしゃり、私もいただきました。
名前も入れてくださるとのことで、苗字を申し上げたところローマ字で綴ってくださいました。
またジャポンも鑑賞していたことも伝えたところ喜んでくださり、そして質問を受けたわけでもないにも拘らず目当てのダンサーについて
つい話してしまい笑、プリンシパル昇格や今回も大活躍である旨を語ってくださり長谷川さん、この度はありがとうございました。
余りに好きな映像があるゆえに鑑賞を見送った昨年末の『美女と野獣』、再演時は美術含めじっくりと拝見いたします。
※今春、もしかしたら同名のバレエは関東外で鑑賞する機会があるかもしれず、その際は詳しく感想お届けいたします。

2日目開演前、上野駅アトレにてローズハイボール。脳内はチャイコフスキーの音楽のみならず、マイク真木さんの名曲も旋回です。半券の絵もロマンを誘います。

初日開演前、薔薇色に近いであろうと苺カクテルを注文。予想通り、薔薇が詰まっているような色彩です。

酒井はなさん、そしてコンテンポラリーを踊る渡邊さんにも興味を示し来場してくださったムンタ先輩と。
管理人のスパークリングワイン、表面張力で耐えうるギリギリまで注いでくださいました!